個人的には、ああいうのでおすすめされた本を実際に読む人って本当にいるの? って感じなのだけれど、どうなんでしょう。ちなみに僕の場合だと、知り合いからおすすめされれば読むけれど、ネットでおすすめされているのはほとんど読んだことがないです。
ただ、僕も院生の端くれであるので、1冊ぐらいそういう本を紹介したいと思います。「学生のうちに読んでおくべき本」というよりは、自分が学部生のときに「読んでおいてよかったなあ」と思っている本です。
それがこちら。
T.W.クルーシアス、C.E.チャンネル(河野ほか訳)『大学で学ぶ議論の技法』。いわゆる「議論学」の本。
日本での出版は2004年。原著の第1版は多分1995年で、現在は第8版(2014年)まで出ている様子。要するにロングセラー。
邦題だと「大学で学ぶ議論の技法」となっているけど、原題は「The Aims of Argument: A Brief Rhetoric」。「大学」という言葉は入っていない。もちろん、もとより大学生向けに書かれた本ではあるのだが、訳者たちによって「大学で」という点が強調されている。これは訳者の教授たちが、現在の日本の大学教育に危機感を抱いているため。
というわけで今回は、①これがどんな本か、②これのどんなところがよかったかの簡単な紹介。学部時代に読んでおいてよかったなあと思う理由なども話します。
1.どんな本なんですか?
「議論 Argument」について書かれた本。「議論」というと皆さん、どんなことを思い浮かべますか? 誰かが出した意見について、ああでもないこうでもない言うあれですね。多くの人が、口頭でのものを思い浮かべるはず。
ただ、この本では、主張を読む・書くことも「議論」に含まれるとされている。論文などを読んで、相手の立場や根拠を探すというのも立派な「議論」であるし、相手を納得させる文章を書くというのも、確かに「議論」であるとのこと。議論の最大公約数的な定義としては、(1)意見を表明すること、(2)その意見を根拠づける理由を1つ以上述べること、が挙げられている。侃々諤々の口頭論議をせずとも、それは立派な「議論」であるということ。
ここでは一応、議論は4つの類型に分けられている。その4つとは、「真理の探究」「納得させること」「説得すること」「交渉すること」の4タイプ。「真理の探究」とは、自分自身や親しい人との対話を通して、自身にとって最も納得のいく答えを導くことを指す。「真理の探究」以外のものだと、自己完結させるのではなく「他者に語りかける」ということが重要な要素となってくる。「納得させること」であれば、他人の意見を変えさせることが目的になるし、「説得すること」になれば、意見だけでなく行動まで変えさせることが目標となる。「交渉」では、相手の意見を変えさせるというよりも、お互いの妥協点を探すことが重要になる。
そんな感じで、一口に「議論」といっても様々あるし、しかもそれは口頭で行われるものに限られない、ということが言われている。特に、論文やエッセイを読み、その主張を精査するのも「議論」の内だとするところが面白い。これは我々が持つような議論のイメージ(相手を論破しようとするもの)を超えているし、どちらかというと、学問や大学での研究一般を指すようなものだと思う。そういう意味で、議論の作法を身につけるというよりは、大学での学びの作法を身につける、という感じになっている。
2.どんなところがよいの?
とはいえ、この辺について書かれた本は、これ以外にもたくさん世に出回っている。「議論」というところに着目しても、福沢一吉『新版 議論のレッスン』(NHK出版)だったり、香西秀信『反論の技術』(オピニオン叢書)だったり。もっと広く「論理的思考」「論文の読み方」的なところでは、戸田山本だったり、それこそ無数にある。僕もほんの一部しか読めていないし、次から次へ出てくるので、到底追いつけていない。
のだが、この本のおすすめポイントを挙げるとすれば、次の2点になる。①指示が具体的であること。「論理的に読む」という点では、単に「5W1Hを意識しろ」としかいわない本もあるのだけれど、この本では具体的なチェックリストなども付いている。特に、今日読み返していて、いいこと書いてあるなあと思ったところがあるので、長いけれど引用する(強調は原文ママ)。
議論を批判的に読む (p28,29)
1.議論のおもな論点が明白に述べられている場合は、それを書留、もしそうでない場合は、余白に自分の言葉で言い換えてみなさい。
2.主張を支えるおもな根拠をさがし、しるしをつけなさい(そんなに多くの理由はみつからないだろう。よい議論は、ひとつの根拠だけを展開し、それを裏づけするのにスペースと努力をさく)
3.その証拠となるものを考え、根拠と証拠がどのくらい裏づけがあるかを余白にコメントとして書きなさい。質的に量的に、証拠となるものを検討しなさい。
4.キー・ターム(重要な概念)と、著者がそれをどう定義しているか(あるいは定義するのを怠ったか)に注意を払いなさい。多くの読者がその定義に納得するだろうか。もっと用語に明確さが必要ならば、あなただったらどのように定義・説明するだろうか。
5.もし書き手がアナロジー(類比)を使っているのなら、比較されているものどうしは本当に類似しているだろうか。問題があったら書きとめなさい。
6.矛盾がないか確かめなさい。引用された証拠が他の証拠と矛盾していないか。
7.論点と根拠のもととなっている前提をたしかめなさい。議論やその根拠は、あらゆる読者が共有しているような前提にたっているか。
8.反対意見が提示されているか。それらは公平に書かれているか。
9.あなたの個人的な反応を考えてみなさい。あなたはどんなことに同意して、どんなことに同意できないのか。その理由は何か。
論点・根拠・証拠などの言葉については、別のところで説明あり(ちょっと疲れてきたので、ここで説明するのは省略)。やっぱり、大変いいことが書いてあるなあと思います。個人的に8番はマジで重要だと思う。
引用したのは「批判的に読む」というところだが、他にも「書く」ときのチェックリストだったり、説得的な議論にするためのチェックリストなどもある。この辺を「論理関係を意識しなさい」とかでぼかすのではなく、はっきり具体的に書いてくれている本はありがたい。
おすすめポイント②は、実践用のサンプルテキストとして、いろんなエッセイ(小論)が用意されているところ。テーマとしては、妊娠中絶や死刑、安楽死の是非についてなど。雑誌に掲載されているような、かなり長めのしっかりした文章が取り上げられている。これだけでも、読み応え抜群である。
あと、我々、死刑や安楽死など、容易に答えの出ない問題については、「人それぞれの考えがあるよね」といった形で議論から逃げがちである。「話し合ったところで答えは出ないでしょ」というか。ただこの本では、そうした難しい問題についても、双方の主張を精査するよう、私たちを導いてくれている。ガッツリした文献を扱って、ちゃんとそれを細かく読むことを推奨しているのがよいなと思う。答えが出ないから・価値観は人それぞれだからと逃げるのではなく「より説得的な議論をしているのはどちらですか」と、そういう姿勢に我々を導いてくれている。
3.学部時代に読んでおいてよかったなあ
長くなってきたのでこの辺でまとめに。この本、学部時代に読んでおいてよかったなあと思うのが、広く学問や研究の在り方一般について、「こういうスタンスでやっていくといいぞ!」というのを示してくれている点。訳者の先生方が怒っているように、こういうの、大学でちゃんと学ぶことはあまりない。本当は基礎セミナーとかで徹底するべきだと思うのだが、あれは先生ごとに方針が違ったりするので、統一的な教育は行われていない。「大学の学問って結局どうすりゃいいの?」というのを、我々はあまり知る機会がないというか、僕は正直この本から学んだことが多い。
僕がこの本に出会ったのは、ゼミの運営に困っていたときであった。あのときは本気で「ゼミでの議論って何?」ということに悩んでいた。一部のよくしゃべる人がトピックを独占して、周りの人はそれについて行けず、しかも何の話をしているのかもよくわからないまま時間が過ぎるということが頻発していたため。全体で議論を構築するというよりは、各自思い思いのことをしゃべるという感じであった。
そういうときにこの本を読んで、なるほどぉおおおおおおアアアアアアアとなった。議論の作法というのがあることがわかったし、どういう問いを立てればよいのかとかも明確になった。前提を確認し、相手の主張とその根拠、それを支える証拠をしっかり確かめるということ。かつ、論文の読み方・書き方なども指南されているので、広く書籍の読み方とかでも学びが多かった。上で引用した「議論を批判的に読む」というのを意識するだけで、だいぶ本の読み方は変わってくるのではないかと思う。あとはまあ、これは多分大学での学問だけに限らず、社会人になってからの会議やビジネスでも役に立つんじゃないかと思う(実際に社会に出ていないのでなんとも言えませぬが)。
ただ反面、僕の議論は男性的過ぎると一回怒られたことがある。僕は議論というものを、前提の共有→主張の確認→その根拠の精査という感じで、ステップアップ的に進めていきたいのだが、これがなんというか、「型に当てはめすぎ」と指摘されたことはある。それだけが議論の在り方ではなくて、もっと自由で柔軟な論議もあるということ。「そんなのがあるなら見せてみろや!!」と思ったりもしたものだが、確かに型に当てはめすぎるのはよくないと思う。あと、僕がこういうやり方にこだわるが故に、そういう議論の仕方を取ってこなかった他の学生と、なんか噛み合わないということはしばしばあった。僕はこの本の作法を一つの「正解」のつもりでやってきたのだが、コミュニケーションの在り方は多様というか、あまり単一のやり方にこだわるのもよくないようである。この辺は悩むこと多し。
4.まとめ
そんな感じで、「学部時代に読んでおいてよかったなあ」と思っている本の紹介でした。久々に読み返しても、この本やっぱいいこと言ってるなあと思う。僕としては全学生に読ませたいぐらいだが、さっきも言ったとおり、一つのやり方の押しつけはよくないので、そこは自重します。でも読んでおいて損はないと思ってます。
最近も戸田山先生の『思考の教室』が出たり、『リサーチの技法』とかの古典があったりするんだけれど、僕はこの本を推し続けたいと思います。途中で書き忘れたけどこの本、「説得すること」のサンプルテキストとして、キング牧師が教会に宛てて書いた手紙とかも収録されているんですよ。獄中で書いたやつです。長いけれど、これも非常にいい文章だった。そんな感じで、「名文が読める」というのも魅力もあり。
大学の学問はどうあるべきか、というところに悩むあなたにおすすめの一冊でした。まだブログの形式に慣れず、読みにくかったらすんません(読み返してもいないので、その辺も許してください。明日校正します)。そんな感じです。
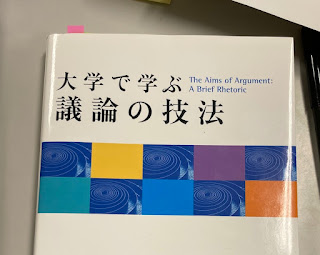




0 件のコメント:
コメントを投稿